市街化調整区域(シガイカチョウセイクイキ)という言葉を聞くけど、
何だかよくわからない……そんな方も多いのではないでしょうか。今回はウチカツを運営するドリームプランニング社長が、市街化調整区域についてわかりやすく解説いたします!
市街化調整区域とは?基本をやさしく解説!なぜ建物を建てるのが難しいの?
「市街化調整区域って…名前からして難しそうだな」と思ったこと、ありませんか?
実は、この区域は都市計画法(第7条)で決められた、市街化を抑制するためのエリアのこと。シンプルに言えば、「これ以上は家を増やさないゾーン」のことを指します。 たとえば、都市部の周辺には田畑や林が残っていて、景観や環境が保たれていますよね。そうした場所の多くが、この市街化調整区域に指定されています。ただ、その分だけ新築や建て替えが厳しく制限されるという特徴があります。
都市計画法の歴史的背景
市街化調整区域と市街化区域の区分が創設され、市街化調整区域において無秩序な建築・開発行為を制限する制度ができたのは、1968年に都市計画法がつくられたときです。
当時は高度経済成長のまっただ中で、あちこちで宅地開発がどんどん進み、街づくりがバラバラになってしまう問題が各地で起きていました。
その流れを整理するために、この制度がスタートしたのです。
市街化区域との具体的な違い
土地を選ぶ上で、この違いを理解することが非常に重要です。
- 市街化区域: 積極的に市街地として発展させる区域。
- 市街化調整区域: 市街化を抑制する区域。
- 非線引き区域: 区域区分を定めていない区域(主に地方部に多い)。
建物の建て替えが難しい3つの主な理由
「え?なぜ建物を建てるのが難しいの?」
初めてこの話を聞くと、たいていの方がまずこう思います。
理由は大きく分けて3つ。
この3つを知れば、「ああ、だからこんなに制限が厳しいんだ」ときっと腑に落ちるはずです。
都市計画法による制限
市街化調整区域では、原則として新しく建物を建てることはできません(都市計画法第34条)。「え、じゃあどんな場合なら建てられるの?」と思いますよね。
例外的に建てられるのは、農家の方の住宅や、地域に必要な公共性の高い施設など、本当に限られたケースが多く、実際は自治体によって許可される建築物は異なります。
一例を挙げると、下記の様なものが建てられる可能性がありますが、詳細はウチカツの登録業者さんに質問機能で問い合わせてみましょう。
都市計画法第34条の許可要件(抜粋)
- 第1号:周辺住民の生活に必要な店舗など
- 第2号:鉱物資源の採取に必要な建築物
- 第11号:市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で五十以上の建築物が連たんしている地域において行う開発行為
- 第12号:開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で定められた区域・目的・用途に合う開発行為
インフラ整備の遅れ
道路や上下水道、電気といった生活インフラが整っていない場所も少なくありません。
「え、インフラがないとどうなるの?」と思われたかもしれません。実際には、こういう問題が出てきます。
インフラ不足による具体的な問題
- 上水道が整っておらず、井戸水に頼るしかないことがある
- 下水道が整備されておらず、合併処理浄化槽が必要で維持管理コストがかかる
- 都市ガスが供給されず、プロパンガスのみ利用可能な場合も
こういう条件だと、たとえ許可が下りても建築コストが大幅に上がってしまうのです…。。
地域の将来像との不一致
行政はエリアごとに「マスタープラン」と呼ばれる土地利用計画を持っています。
「マスタープランって何?」と思う方もいるかもしれませんが、簡単に言うと、その地域を将来どう使っていくかを決めた設計図のようなものです。
マスタープランにおいては、立地適正化計画などで市街化区域内に都市機能誘導区域や居住誘導区域などに都市機能が集約されおり、市街化調整区域においては、居住が誘導されておらず行政の思いとは異なることも建物を建てる事が難しい理由となっております。
市街化調整区域のメリット
「制限が多い」と聞くと、なんとなくマイナスなイメージが浮かびますよね。 でも実は、その裏には“意外なメリット”が隠れているんです。
土地価格が比較的安い
「え、そんなに安くなるの?」って驚く方も多いんですが、市街化区域に比べると価格はかなり低めです。
広い土地をお得に手に入れられる可能性があるのです。
たとえば…(地域によって差はありますが)
- 市街化区域:坪単価 15〜20万円
- 市街化調整区域:坪単価 3〜8万円
隣接した場所でも市街化区域と市街化調整区域で価格差にこの位の開きがあることがあり、同じ予算でもより広い敷地で、のびのびした暮らしを実現できるのです。
自然環境が豊か
「静かな場所で暮らしたい」「緑の多い場所が好き」って方には、かなり魅力的です。
農地や林が多く、都会の喧騒から離れた落ち着いた日常を送れます。
朝、窓を開けたら鳥のさえずり…なんて生活、ちょっと憧れませんか?
固定資産税が安い傾向
「税金も安くなるの?」と思った方もいらっしゃると思いますが、市街化区域より固定資産税は安くなる傾向にあります。
また、都市計画税(0.3%)は非課税であることが多く、その分は安市街化調整区域のデメリット
「もちろん、いいことばかりじゃないんですよ…」
現実には、ちょっと覚悟して向き合わなきゃいけない課題もあります。
建築・建て替えの制限
「え?建物が建てにくいことは分かったけど、建て替え出来ない事もあるの?」
と思う方もいらっしゃると思いますが、それが一番びっくりされるポイントなんです。
ざっくり言うと…
- 新築は原則NG(ただし条件を満たせば許可が出ることも)
- 農家住宅・分家住宅として建物が建てられている場合、農家でない方が建て替える事は原則不可(属人性と言い、農家の人だから許可された建物であり、他の方は建て替えはもちろん利用も出来ません)
- 他の用途(例えば店舗兼住宅などを特例で建てた場合など)で建てらられた場合も、属人性がある場合は原則建て替え不可
実は用途変更といって属人性によって許可された建物を適法に建て替える方法もあるのですが、そこがまたハードルで…。
そもそも、その建物が適法に利用されていたか、買主がその地域に何年以上住んでいるかなど、様々な証明が必要な上に、申請から許可が下りるまでに数ヶ月かかることもありますし、正直、必ず許可が下りない可能性の方が大きいのです。
売却が難しい
「売ろうと思えばすぐ売れるでしょ?」と思われるかもしれませんが…実はそうでもありません。
理由は単純で、買ってくれる人が限られてしまうからなんです。
例えば…
- 住宅ローンが組みにくく、金融機関が限られることもある
- 「再建築不可」になるかもしれないという事を理解してくれる人じゃないと契約できない
- 不動産会社によっては取扱い自体を避けるところもある
市街化区域の土地なら3ヶ月くらいで売れることも多いですが、市街化調整区域だと1年以上かかることもザラです。
市街化調整区域の活用方法や賢い使い道
ここまで、読んできて市街化調整区域で建物が建っていないところや、建て替えが出来ないところ、属人性があり売買しても建物が利用出来ないところについては、「活用方法が無いのでは?」と思われるかもしれません。
でも…実はそんなことはないのです。
ちょっと発想を変えてみるだけで、「え、こんな使い方があったの?」という活用方法が見えてくることもあります。
農業・園芸関連での活用
- 家庭菜園や自給自足の野菜作り
- 本格的な農業経営
- 体験型の農園運営
- 観光農園(いちご狩り、ブルーベリー狩りなど)
「自分で野菜を作ってみたい…」「農園ビジネスに挑戦してみたい…」という方には、ぴったりの使い道です。
事業用地としての活用
- 倉庫や資材置き場
- 運送業の車両基地
- 農機具の格納庫
- リサイクル業の分別・保管スペース
ただし、「ここで事業をやってもいいの?」という点は要注意。
近隣への配慮は欠かせません。
再生可能エネルギー事業
- 太陽光発電(自治体の許可が必要)
- バイオマス発電
「こんな場所でも、エネルギー事業に使えるんだ…」と驚く方も多いでしょう。
行政の許可が非常に難しい所ではありますが、地域の理解があれば、可能性は意外と広がります。
市街化調整区域でも売却できる?実際の売却候補について
市街化調整区域の不動産の売却先とその特徴について少し纏めてみます。
A.専門買取業者
・直ぐに買取が出来る。
B.一般の不動産会社
・取扱いをする会社が少ない
C.個人購入者
・建て替えや用途変更の場合は都市計画法第34条の許可が売買の条件になることもある
D.法人・事業者
・倉庫や資材置き場などの用途が許可基準に合致しなければ利用不可。(個人購入者と同じく許可が条件となり売買が難しい)
E.農家・農業関係者
・農地を売却する場合は農地法第3条の許可を取得し、農業従事者への売却が可能
・農家や農業関係者自体が少ない
F.隣の人(隣接する第三者)への売却
・市街化調整区域内の許可は「属人的許可」が多く、許可を受けた本人以外が建物を利用してはいけない。
・売却時は、隣人を含む買主に用途変更(属人性の解除)の必要性を説明し、「用途変更が出来なければ契約解除」とする特約を付けることが重要。
売却時の注意点
売却の前には、「え、そんな調査まで必要なの?」と思うくらい、事前準備が大切です。
具体的には…
- 都市計画法による制限の確認
- 農地法での制限があるかどうか
- 土壌汚染がないか
- 境界を確定するための測量
- 各種許可が買主に引き継げるかどうか
- 私道に関する負担や権利関係
- 災害リスクがないか
しかし、不動産SNSウチカツを利用して相談すれば、難しい事前準備は不要で、専門業者さんに調べてもらえることもあります。
調査で悩んだら、ウチカツに市街化調整区域の相談をしてみましょう。
市街化調整区域のお悩みなら、まずは何でもウチカツへご相談を
以上、市街化調整区域について言葉の定義からメリット&デメリット、活用・売却方法などを徹底的に解説してきました。
長文となってしまいましたが、すべてお読みくださった方は、本当にありがとうございます。市街化調整区域についてお悩みごとがございましたら、まずはどんな些細なことでも業界初の不動産SNSウチカツ(UCIKATU)へご相談ください。
ウチカツを利用すれば、匿名かつ無料で市街化調整区域のご相談が可能です。 お困りの市街化調整区域の物件があれば、お気軽に相談してみてください。
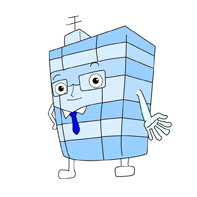
完全無料なのもうれしいね!(※一部任意の有料プランあり)
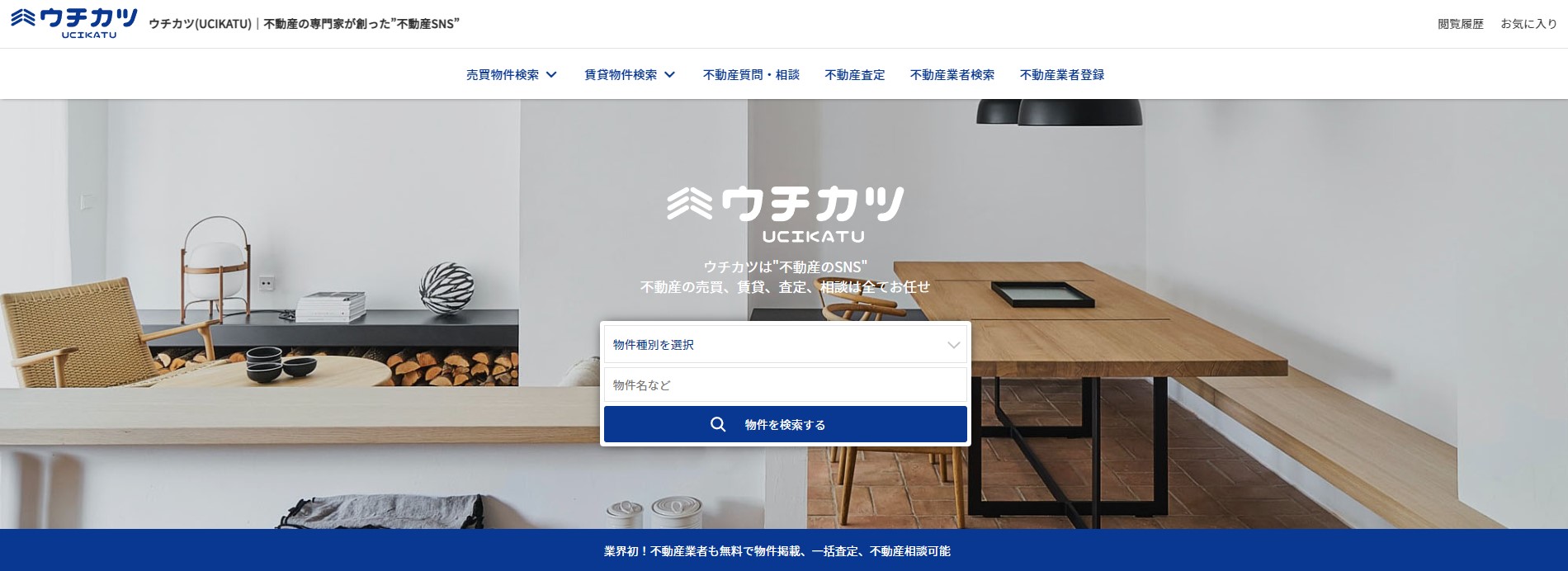
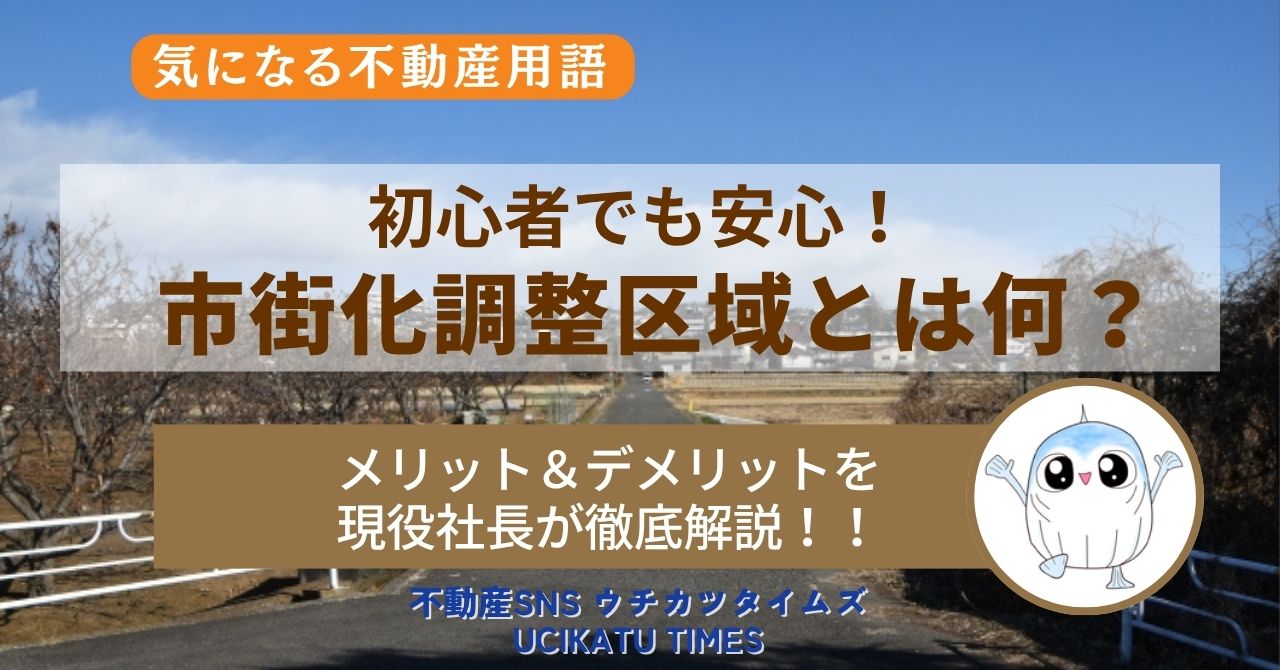


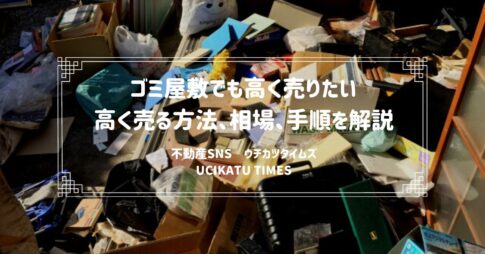

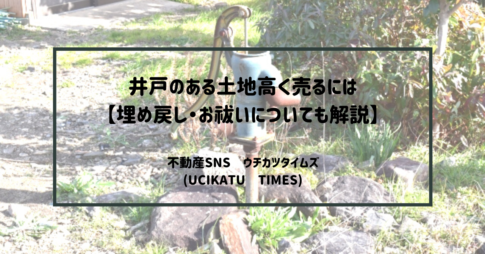


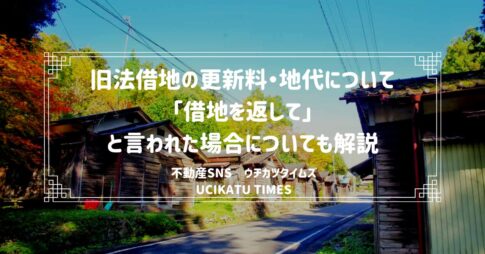
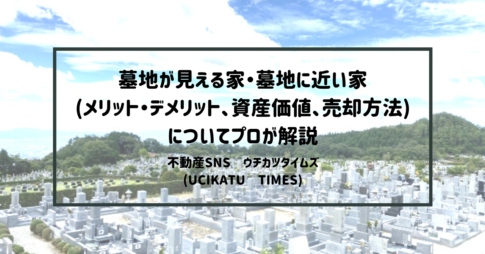

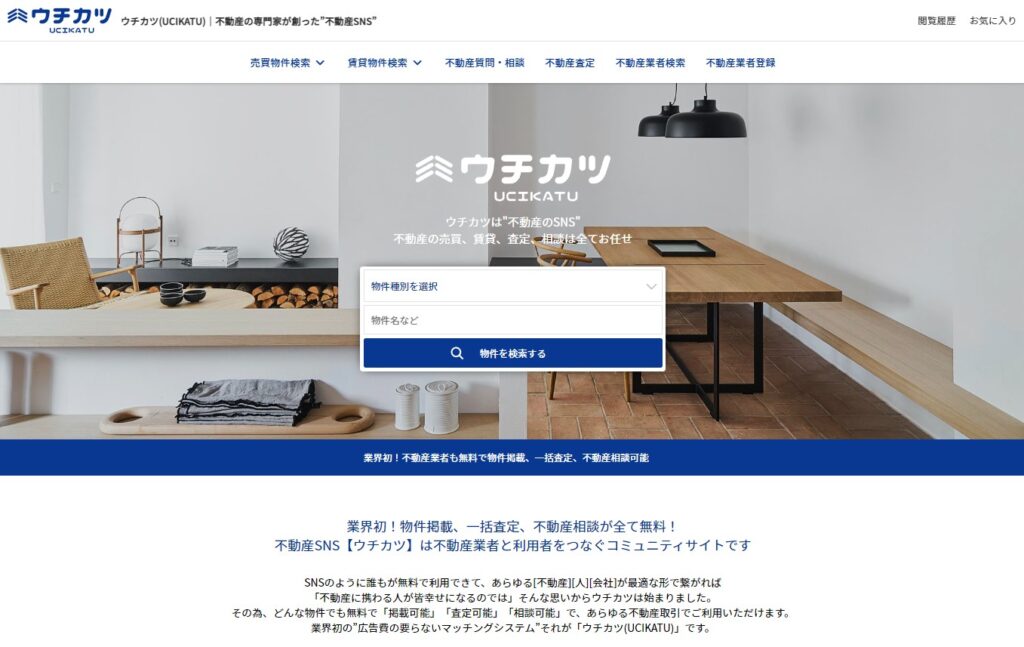

ウチカツオもウチカツをのぞいてみるよ!