再建築不可物件(さいけんちくふかぶっけん)という言葉を聞くけど、
何だかよくわからない……そんな方も多いのではないでしょうか。今回はウチカツを運営するドリームプランニング社長が、再建築不可物件についてわかりやすく解説いたします!
再建築不可物件とは?
「再建築不可物件」とはどんなものか、まずは基本から見ていきましょう。「難しそう…」と思うかもしれませんが、大丈夫。中学生でも理解できるように、シンプルにご説明します。
基本的な定義
再建築不可物件とは、「今ある家を壊しても、新しい家を建てることができない」不動産のことです。見た目はふつうの住宅と変わらないことが多く、実際に人が住み続けることも可能です。
ただし、建物を新しく建てるには「建築基準法」というルールを守る必要があり、それを満たしていない土地では、新築工事が認められません。だから、原則として「建て替え」ができないのです。
全国にどのくらいある?
「そんな珍しい物件、ほんとにあるの?」と思うかもしれませんが、じつは全国で430万戸以上存在しています。特に東京や大阪、名古屋など、昔ながらの住宅街に多く見られます。
これは、戦後の住宅不足により、細い道沿いにもたくさんの家が建てられたことが背景にあります。当時は問題なかった道や土地も、今の厳しい法律では再建築ができないとされてしまうのです。
どうして建っているのに再建築できない?
「でも、もう家が建ってるよね?」という疑問もありますよね。
これは、「その当時のルールでは合法だった」からです。昔は今ほど都市計画の制限が厳しくなく、その時代の条件で建築許可が下りていたケースが多いんです。
ところが、その後に都市計画法が改正され、同じ場所で新しく建てることが制限されるようになりました。
そのため、厳しい基準ではなかったため、合法的に建てられた家も多くあります。また、建て替えはできなくても、修繕やリフォームならOKというケースもあり、現在も多くの人が住み続けています。
建て替えできない2つの理由
なぜ再建築ができないのか?理由は主に2つあります。少し法律の話になりますが、思い浮かべながら読んでみてください。
接道義務を満たしていない
建築基準法では、建物を建てるには「幅4m以上の道路に、土地が2m以上くっついていないといけない」と決まっています。これを「接道義務」といいます。
細い路地や、奥まった土地(旗竿地=はたざおちなど)ではこの条件を満たしていないことがあり、そうした場合は新しい建物が建てられないのです。
市街化調整区域にある
「市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)」というエリアにある土地も再建築ができません。ここは、都市の広がりを制限したり、農地や自然を守るために建物の建設が原則禁止されている地域です。
つまり、建物を建てることそのものが制限されているエリアなので、基本的に建物を建てる事が制限されています。
再建築不可物件のメリット
「建て替えできない=デメリット」と思われがちですが、実は他の物件にはない魅力もあるんです。この章では、再建築不可物件の“意外な良いところ”を紹介します。
価格がとても安い!
建て替えできないという理由だけで、同じ場所のふつうの物件と比べて、価格が半額以下になることもあります。たとえば、東京23区内でも1,000万円以下の物件が見つかることがあります。地方では100万円以下のケースも!
税金が安くなる
建物や土地の価値が低く評価されるため、「固定資産税」や「都市計画税」といった税金も安くなります。年間1〜2万円ほどで済む物件も多く、長く所有する場合には大きなメリットです。
投資のスタートとして最適
自己資金だけで購入できる価格帯が多く、不動産投資初心者にとってはチャレンジしやすい選択肢です。リフォームして貸し出せば、家賃収入を得ることもできます。
再建築不可物件のデメリット
もちろん、デメリットもあります。買ったあとに「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、ここでは注意点をしっかりお伝えします。
建て替えできないリスク
火事や地震などで家が壊れてしまっても、新しく家を建てることができません。つまり、万が一の時に「住める家がなくなってしまう」というリスクを抱えることになります。
住宅ローンが使えない
多くの銀行では、再建築不可物件には住宅ローンを出してくれません。原則、現金で買う必要があります。また、「フラット35」などの公的ローンも使えない場合があります。
売るときに苦労する可能性
買い手が限られるため、すぐに売れなかったり、思っていたよりも安い価格になってしまうこともあります。将来的に資産価値が上がりにくい点も要注意です。
再建築不可物件の活用方法
「建て替えできない=使い道がない」と思っていませんか?実は工夫次第で、いろいろな使い方が可能です。実例をもとにご紹介します。
今の家をリフォームして住む
一番多い使い方です。水回りや内装をリフォームするだけで、快適な住まいに生まれ変わります。建て替えできなくても、暮らしやすく整えることは十分可能です。
賃貸として貸し出す
空き家をリフォームして、家賃収入を得る方法です。ファミリー向けの戸建て、シェアハウス、テレワーク拠点など、使い方は様々です。
お店や倉庫として使う
自営業の拠点や、趣味のスペースとして活用することも可能です。小さなカフェ、美容室、アトリエ、ガレージなど、建物がすでにあるからこそ実現しやすい活用法です。
再建築不可物件を建築可能にする方法
「再建築不可」といっても、必ずしも“永遠にダメ”というわけではありません。一定の条件をクリアすれば、再建築が可能になるケースもあります。
43条2項の許可を得る
建築基準法では4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接道していないと建て替えが出来ないのですが、特例として自治体で間口1.5mでも建て替えができるなど、一定の基準を定めている事があり、この基準を満たしていれば建て替え出来る事があります。
隣地を買う
隣の土地を購入して接道面積を広げることで、建築基準をクリアできる可能性があります。旗竿地など、接道がギリギリの土地では特に有効な手段です。
道路の整備協議
市区町村と協議して、私道の整備や公道への接道確保を目指す方法もあります。ハードルはやや高いですが、不可能ではありません。
売却時のポイント
「この物件、売れるのかな?」と不安に思う方へ。ここでは、少しでも有利に売却するためのコツと、頼れるパートナーの選び方をご紹介します。
隣地とのセット販売
隣の土地を持っている人にとっては、再建築不可物件にも価値があります。一緒に売ることで建築可能になり、価格アップが期待できます。
地元の不動産会社に相談
地域に詳しい不動産会社であれば、再建築不可物件(さいけんちくふかぶっけん)の扱いにも慣れていることが多いです。相談しやすく、的確なアドバイスがもらえるでしょう。
買取専門業者に売る
「早く売りたい」「管理が大変」という方は、再建築不可物件を専門に扱う買取業者に相談するのも1つの手です。価格はやや低くなるものの、スムーズに処分できます。
再建築不可物件の相談は「ウチカツ」へ!
今回は再建築不可物件のメリットやデメリットについて解説してまいりました。
再建築不可物件に関するお悩みや疑問は、業界初の不動産SNSウチカツ(UCIKATU)への無料相談がおすすめです。
ウチカツは無料&匿名(登録不要)で利用可能。回答者は登録された不動産会社のプロばかりですから、信頼性の高い回答が得られます。
便利でお金のかからない不動産SNSウチカツを、どうかご利用くださいませ!
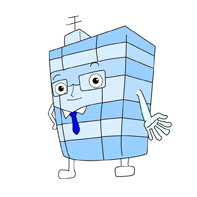
完全無料なのもうれしいね!(※一部任意の有料プランあり)
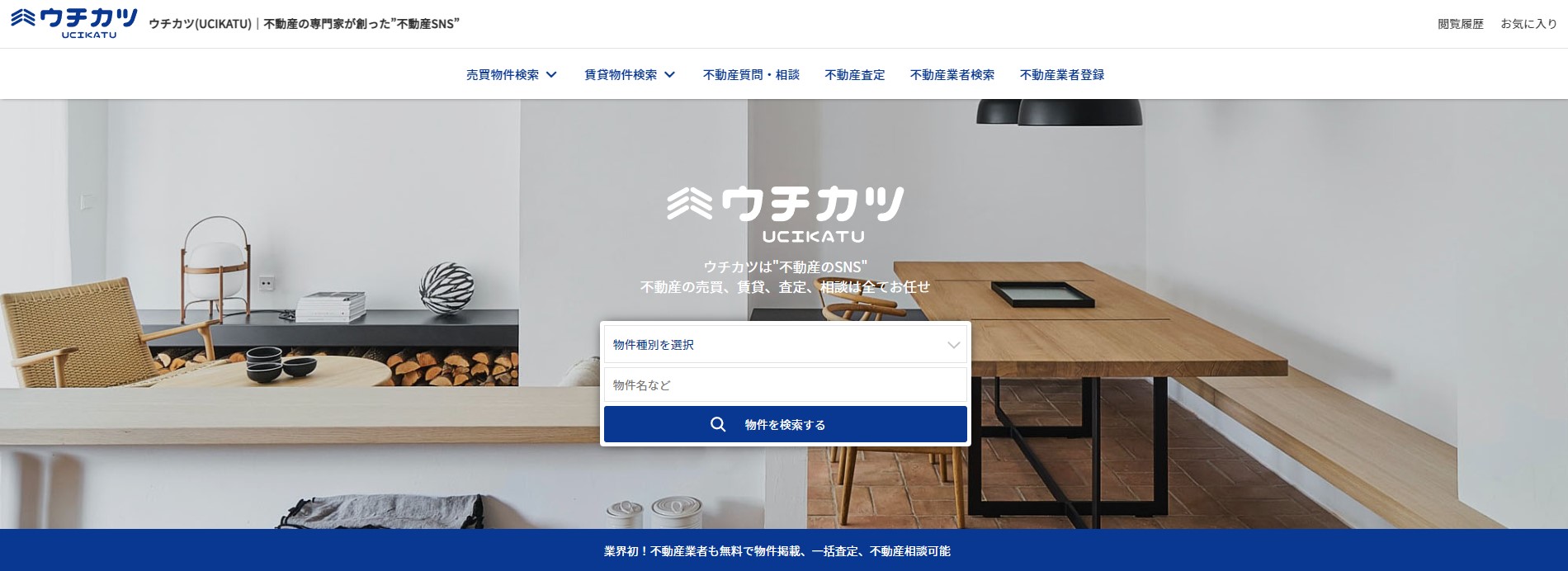


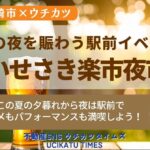
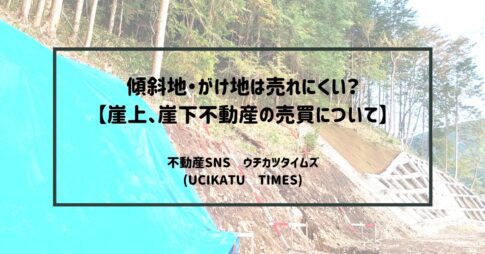

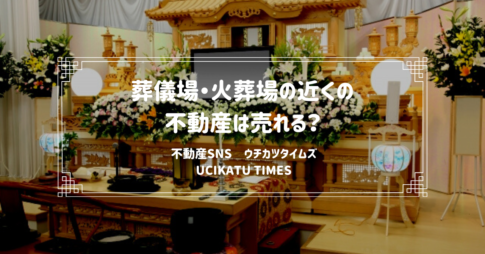
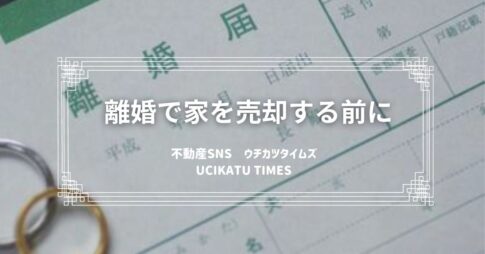

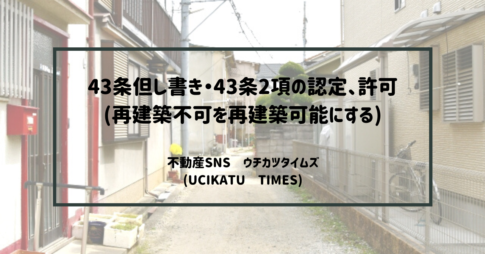
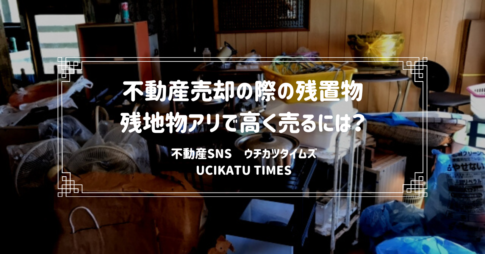

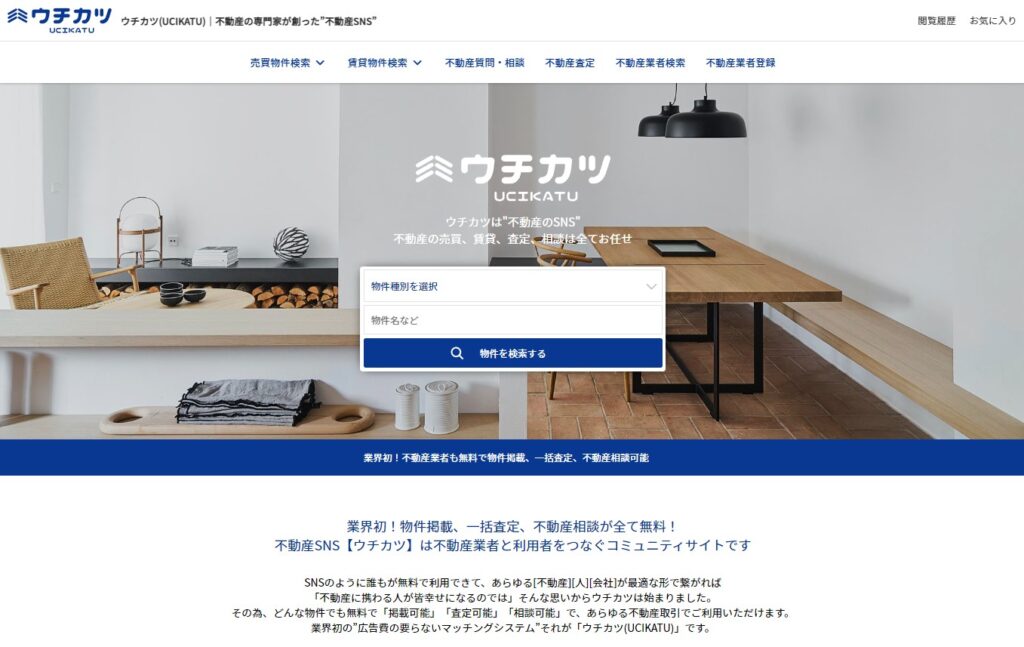

ウチカツオもウチカツをのぞいてみるよ!